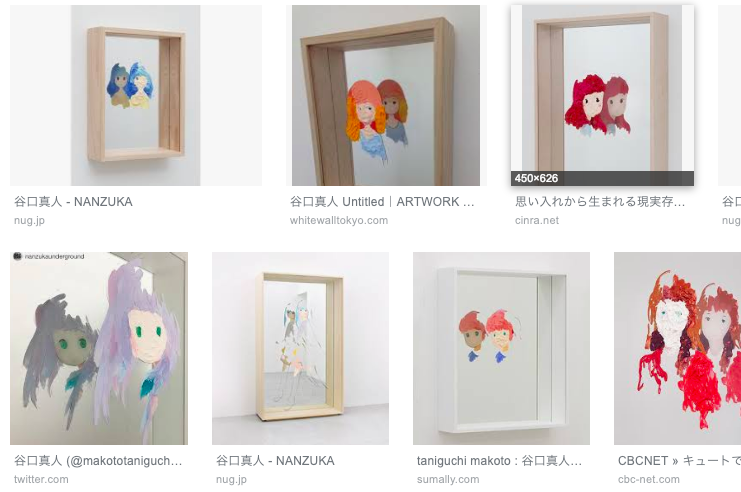20世紀ドイツの思想家・批評家として知られるヴァルター・ベンヤミンは、1936年に「複製技術時代の芸術作品」(以下「複製技術論」)と題された有名な論考を発表している。この論考の末尾でベンヤミンは、ファシズムが進める「政治の美学化」に対して、コミュニズムによる「芸術の政治化」を主張した。
「政治の美学化」とは、ごく簡単に言うと、絵画や音楽などの美的・芸術的な手段を用いて、人々を政治的に動員することである。ベンヤミンによれば、この傾向は最終的に戦争へと行き着き、人類は自分自身の絶滅を美的に享受することになるのだという。
では、これに対抗する「芸術の政治化」とは、具体的に何を指しているのか。芸術を通じてファシズムへの反対を呼びかけることだろうか。だが、それでは単に逆向きの「政治の美学化」にすぎない。ベンヤミンの言う「芸術の政治化」は、ファシズムに対抗するものでありながら、芸術を政治的宣伝や動員の道具として利用することではない。とすれば、それはいったい何を意味しているのか。
「複製技術論」では、踏み込んで説明されていないこともあり、この問いに対する答えは必ずしも明確ではなかった。本稿の目的は、同論考をベンヤミンの他のさまざまなテクストと関連づけることで、彼が提唱した「芸術の政治化」の内実を明らかにすることにある。
議論に入る前に、「複製技術論」の成り立ちについて簡単に確認しておこう。このテクストは、ナチス政権から逃れたベンヤミンが、亡命先のパリで書き上げたものである。現在までに三種類のドイツ語稿(初稿1935年、第二稿1935~36年、第三稿1939年)に加えて、ピエール・クロソフスキーとの共訳によるフランス語稿の存在が知られている。
ベンヤミンの生前に発表されたのは、ドイツ語の第二稿をもとにしたフランス語稿のみだが、論考を掲載したフランクフルト社会研究所の意向に沿って改変が加えられているため、現在ではドイツ語の第二稿および第三稿が事実上の完成稿と見なされている。本稿では、とくに断りのないかぎり第二稿を参照する。その理由については後述することにして、次に、同論考に対する今日までの評価を見ていくことにしよう。
「複製技術論」はベンヤミンの多岐にわたる仕事のなかでも、とりわけ広く読まれているテクストのひとつである。しかし、同論考が発表される以前から、その内容や主張の妥当性を疑問視する声も少なくなかった。
10歳年下の盟友であるテオドール・W・アドルノは、ベンヤミンから送られてきた草稿にかなり手厳しい批判を加えている。一貫して二項対立的に見えるベンヤミンの議論に対し、アドルノは「もっと多くの弁証法を」と繰り返し要求したが、同様の疑念を抱いたのは彼ばかりではなかった。
アドルノと並び、ベンヤミンの古くからの友人であるゲルショム・ショーレムは、「複製技術論」のテクストそれ自体が引き裂かれていることを指摘する。ショーレムによれば、同論考は複製技術による「アウラの凋落」について論じた前半部と、映画の政治的・社会的機能について論じた後半部とのあいだに、深刻な内部分裂を抱えているという。彼は前半部の形而上学的な議論を高く評価する一方で、コミュニズムによる「芸術の政治化」を主張する後半部の記述を「魅惑的な誤り」と切り捨てる。
他方で、ベンヤミンがマルクス主義へと傾倒するきっかけとなった劇作家のベルトルト・ブレヒトは、ショーレムとは対照的に、テクストの前半部に見られる「アウラ」概念を「まったくの神秘主義」と非難している。つまり「複製技術論」は、後にユルゲン・ハーバーマスが指摘するように、ベンヤミン生来の神学的・神秘主義的な傾向と、1920年代以降のマルクス主義的な立場を統合しようとする、不可能な試みとして位置づけられるのだ。
そしてこの分裂は、今日にいたるまで解消されていないように思われる。たとえばメディア論や記号論の領域では、前半部の「アウラの凋落」に関する議論が繰り返し参照されるのに対し、後半部の映画についてのマルクス主義的な分析のほうは、ほとんど取り上げられることがない。また近年では、トム・ガニングをはじめとする初期映画研究の文脈で言及されることも少なくないが、「ショック」や「気散じ」といった個別の概念への注目にとどまり、映画の政治的な位置づけについてはやはり語られていない。テクストそれ自体の内部分裂という問題は、事実上棚上げされているのである。
本稿では「芸術の政治化」を論じるにあたって、後半部の映画に関する議論を主題的に扱うことになるため、この問題を避けて通ることはできない。だが、ハーバーマスの言うように、「複製技術論」の前半部と後半部、すなわち神学とマルクス主義は、本当に対立関係にあるのだろうか。両者は本来緊密に結びついているにもかかわらず、あえてそのことが見えづらくなっているのではないか。
ベンヤミン晩年の断章集「歴史の概念について」(1940年)には、マルクス主義と神学との関係について、印象的なメタファーを交えて語った箇所がある。彼は「トルコ人」と呼ばれた有名なチェスの自動人形を念頭に置きながら、歴史的唯物論(マルクス主義)をその人形に、そして神学をテーブルの下からひそかに人形を操る「せむしの小人」にたとえて次のように述べている。
〈歴史的唯物論〉と呼ばれるこの人形は、いつでも勝つことになっている。この人形は誰とでも楽々と渡りあえるのだ。ただし、今日では周知のように小さくて醜くなっていて、しかもそうでなくても人の目に姿を曝してはならない神学を、この人形がうまく働かせるならば、である。
このチェス人形は常に勝利することができる。けれども、それは操作される側の人形(唯物論)が、操作する側の小人(神学)をうまく働かせるかぎりにおいてである、という。この転倒した不思議な主従関係は、その数年前に書かれた「複製技術論」にも同様に当てはまるのではないか。言い換えれば、同論考に見られる内部分裂は、マルクス主義と神学との対立や矛盾が露呈したものというよりも、両者の関係性についてのベンヤミン自身の意図的な配置によるものなのではないか。彼は自身の神学を「働かせる」ために、マルクス主義という人形を必要としたのだ。
とすれば、1920年代後半以降のベンヤミンのマルクス主義への接近は、単なる転向や政治的妥協の結果として見られるべきではない。そうではなく、ノルベルト・ボルツが指摘するように、神学を世俗化する試みとして積極的に理解されなければならない。
「複製技術論」前半部から後半部への、すなわち「アウラの凋落」から「芸術の政治化」への断絶ないし飛躍は、テクストに明示的に表れることのない、隠された神学によって結びつけられている。したがって、テクスト後半部に見られる映画への過剰なほどの期待は、しばしば批判されるようなマルクス主義への素朴な信頼によるものではない。それはむしろ、そのような楽観論を読み込むことを可能にする、神学的な思考の枠組みによるものと考えるべきだろう。
「芸術の政治化」の内実を問うためには、ベンヤミンが人形を通じてテーブルの下の小人を働かせる、とはつまりマルクス主義を通じて神学を機能させる、その具体的なメカニズムを明らかにする必要がある。本稿でドイツ語の(第三稿ではなく)第二稿を取り上げる理由はここにある。というのも、たしかに第三稿には、第二稿にはないさまざまな補足や修正が加えられているが、その一方で、テクストの内部分裂を解消するための鍵となる概念、すなわち「遊戯」に関する記述がほぼすべて削除されているからだ。
これに対して第二稿では、本文や註釈で繰り返し遊戯のモチーフが登場し、テクストの前半部と後半部を接続する、蝶番としての役割を果たしている。「複製技術論」における「せむしの小人」とは、第三稿には見られない遊戯概念、とりわけ「自然と人類との共演(共同遊戯)」というきわめて神学的な構想にほかならない。第三稿から遊戯に関する記述が削除されているのは、アドルノらの批判に応えるという意味ではもちろん、小人としての神学を完全に不可視化するためでもあったのではないか。
いずれにせよ、「複製技術論」の内部分裂に架橋し、後半部における「芸術の政治化」の内実を明らかにするためには、第二稿に頻出する遊戯概念に注目する必要がある。そして、近年におけるその最も重要な成果が、同論考についてのミリアム・B・ハンセンによる包括的な読解である。
ハンセンは遊戯をはじめ、第二稿に登場する重要概念をいくつも取り上げ、「アウラの凋落」に偏向した従来の解釈とは一線を画した議論を展開している。本稿もまたハンセンの読解に多くを負っているが、その一方で、彼女の議論はあくまで個々の概念の詳細な解説にとどまっており、「複製技術論」を支えるベンヤミンの神学的思考の道筋を説明するにはいたっていない。それぞれの概念の由来や用法、またはその多義性を強調するあまり、それらを内在的に結びつけている理論的な枠組みを取り逃がしているように思われるのだ。
この問題を明らかにするためには、ベンヤミンが、革命の主体となるプロレタリア大衆をひとつの「身体」として捉えていたことを理解しておく必要がある。すでに何度か指摘されているように、彼は1920年代前半頃から「人類の身体」という神学的・宇宙論的な構想を抱いており、これが1920年代後半以降、マルクス主義的な革命の理論へと重ね合わされていく。
「複製技術論」においては、革命が集団的身体による「自然との共演(共同遊戯)」として新たに位置づけられるのだが、そのこと自体はテクストのなかでは明示されず、大衆の「器官」や「神経刺激」といった生理学的な用語によって暗示されるにとどまっている。これが同論考における、隠された神学的次元である。したがって、ベンヤミンのいう「芸術の政治化」とは、「自然との共演(共同遊戯)」を可能にする集団的身体を組織するために、芸術、とりわけ映画を役立てることを意味する。彼の考えでは、映画はこの遊戯のための格好の練習道具なのだ。
本稿ではこのような前提に基づき、「複製技術論」後半部の議論をベンヤミンの他のさまざまなテクストと関連づけ、映画による集団的身体の組織化プロセスを説明したものとして読み解いていく。それでは、はじめよう。